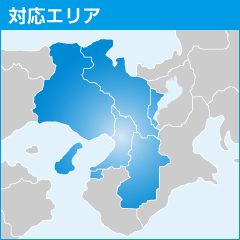交通事故にあって傷害を負った場合に、その治療のために輸血が必要になることがあります。その治療のための輸血により、肝炎に罹患してしまったようなことがあります。輸血後に肝炎に感染することは、現在だいぶ減ってはいますが、それでも完全になくなったわけではありません。
1 輸血後の肝炎
肝炎ウイルスに汚染された他人の血液の輸血を受けることで、B型肝炎やC型肝炎に感染することがあります。現在は、献血用血液から感染血液を除くスクリーニング法が採用されていますので、昔と異なり、輸血により肝炎に感染することは少なくなっています。
2 肝炎になった場合の後遺障害等級
交通事故の治療による輸血等で肝炎になった場合の自賠責後遺障害等級一覧は、以下のとおりです。肝硬変や慢性肝炎などを発症しているかどうかが等級に影響を与えます。
|
等級 |
後遺障害の内容 |
|
第5級3号 |
機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
|
第7級5号 |
機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
|
第9級11号 |
機能に障害を残し、服することのできる労務が相当な程度に制限されるもの |
|
第11級10号 |
機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
自賠責後遺障害等級以外でも、裁判例では相当等級として評価している事例もあります。
3 輸血による肝炎と交通事故との因果関係
交通事故後に治療中行った輸血によって肝炎になった場合に、交通事故との因果関係があるのかについて争われることがあります。
(1)岡山地裁平成3年9月20日判決(交民 24巻5号1080頁)
岡山地裁平成3年9月20日判決の事案は、交通事故で脾臓摘出の手術を受けることになり、輸血をした際に肝炎に感染したことが、交通事故と因果関係があるのか争われました。
上記岡山地裁は、肝炎は、交通事故によって直接生じたものではなく、交通事故後脾臓摘出手術を受けた際になされた輸血が原因となって起こったものであり、被告らは交通事故との因果関係を争っているが、交通事故を原因とする脾臓摘出手術のために輸血が必要であったことが認められ、また輸血により肝炎が併発したことが医師の過失によるものと認めるに足りる証拠も存しないから、交通事故と肝炎との間には相当因果関係が存在するものというべきであるとしました。
(2)岡山地裁平成10年3月26日判決(交民31巻2号512頁)
岡山地裁平成10年3月26日判決の事案は、交通事故により、頸部・胸・腹部打撲、出血性ショック、肝破裂、膵・腎損傷、右肺挫傷、血気胸、右第四・五・六肋骨骨折の傷害を受け、出血性ショック死を防止するため及び治療のための手術で輸血を行ったところ、C型肝炎を発症したというものです。
上記岡山地裁は、交通事故にあうまでは被害者は健康そのもので、C型肝炎罹患の兆候は全く見られなかったこと、一般に、大量輸血後に輸血が原因でC型肝炎に感染する危険性もないではなく、C型肝炎の原因についても、事故後の治療の際の輸血以外には考えられないことを認めて、治療のために大量の輸血を必要としたのは交通事故による受傷に起因するから、C型肝炎への罹患及びそれによる肝機能障害の発生と交通事故との間には、相当因果関係があると認定しました。
4 肝炎に関する裁判例
(1)大阪地裁平成7年12月4日判決(交民28巻6号1675頁)
大阪地裁平成7年12月4日判決は、輸血後肝炎で肝炎に感染しましたが、GOT・GPTの数値が正常な範囲内であったため、自賠責からは非該当とされた事案です。
上記大阪地裁は、インターフェロン治療後も、HCV(C型肝炎ウイルスのキャリア)であって、投薬ないし注射等の治療を継続し、過労ないしアルコールや刺激物の摂取を避ける生活をしなければ、肝臓の炎症が強くなり、将来肝硬変ないし肝臓癌となる時期が早まってしまう危険がある状態であるから、治療の継続、過労の回避及び食事の制限が不可欠な症状といえ、その症状は将来的に残存する蓋然性が認められるから、このような症状自体を後遺障害と評価すべきであるとしたうえで、時間外労働が制限されていること、ほとんど毎日の通院によって肝炎の炎症を抑制していること等からすると、後遺障害12級に該当するものと認めるのが相当であるとしました。また、労働能力喪失率を15%と認定しました。
(2)大阪地裁平成10年9月1日判決(交民31巻5号1330頁)
大阪地裁平成10年9月1日判決は、慢性C型肝炎として自賠責後遺障害等級11級11号(当時の基準)に該当し、他の症状との併合で後遺障害10級に認定された事案です。
上記大阪地裁は、肝機能も採血による経過観察を続けており、一応正常範囲内に納まってはいるが、C型肝炎ウイルスキャリアであるため、手術等の仕事中に自分が出血をしてしまうと患者に感染するおそれがあるので、気をつけながら仕事をしている状 態であったこと等を考慮して、労働能力喪失率を20%とし、労働能力喪失期間を就労可能年限である67歳までの31年間と認めました。
5 関連記事・コラム
(弁護士中村友彦)